
医療法人みなとみらいグループ職員向け・第4回「糖尿病ハンズオンセミナー」を開催しました
日々の診療に直結する内容について学びを深める、第4回「糖尿病ハンズオンセミナー」を開催いたしました。当日は、糖尿病内科担当の診療部長・太田一樹医師が講師を務め、「薬物療法」について最新情報を交えて講演いたしました。 ■日時:2026年2月18日(水)18:15~19:00■講師:太田一樹先生(診療部...
Better Sleep,
Better Future
医療法人みなとみらい
漏れのない医療、ミスのない医療、わかりやすい医療、
そしてうれしい医療をめざしています。
いつも、笑顔を心がけています。
通われる皆様とともに、医師、スタッフ全員で、
ワンチームで取り組んでいます。
医療の質や利便性の向上に努めています。
Illness &
Wellness
私たちは、いつも健康であることを目標に診療しています。糖尿病・生活習慣病・甲状腺疾患と睡眠時無呼吸症候群の専門治療を行っています。治療を継続していく上での悩み、不安、疑問、日常のケアなど、療養上の困難に対し、チームで患者さまをサポートします。
1型・2型糖尿病、糖代謝異常を対象に、最新の治療薬や機器、療養サポート、栄養相談を組み合せた診療を実施。
脂質異常症、高血圧、痛風、脂肪肝など、偏食・運動不足・飲酒・喫煙・ストレス等と関連する異常や症状が対象。
バセドウ病や橋本病、甲状腺腫大・腫瘍などの各種甲状腺疾患、および、甲状腺機能異常による不妊を専門的に診療。
生活習慣病や循環器疾患を招く恐れのある睡眠時無呼吸症候群を、睡眠学会認定技師が評価し、最適な治療を導入。
「105歳までアクティブ」を目標に、個別化されたヘルス&ウェルネスプランを作成・実行するメディカルケアサービスを提供しています。
最先端の検査で得られるメディカルデータと、ヘルスケアデバイスから取得する日常データをもとに、現状を正確に知り、問題点を抽出し、ライフスタイルを改善しながら、最新の個別化治療を行います。
1秒ごとに身体活動データを取得・収集できる高精度センサーを搭載したスマートリングを着用。睡眠・身体の状態を可視化し、精緻な分析を行います。
毎月、パーソナルドクターとの面談を実施し、代謝機能、免疫機能、循環機能のほか、筋肉と脂肪の部位ごとの変化をチェックします。
臓器年齢、テロメア長、腸内細菌DNA分析、代謝分析などの検査のほか、全ゲノム解析、全遺伝子発現解析、ガン遺伝子のリキッドバイオプシーも行えます。
東京の都心部、神奈川県の横浜市と湘南地区を中心に、睡眠を基本に糖尿病、甲状腺を専門とする11クリニックを運営しています。

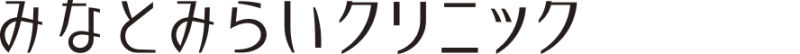
〒220-0012 神奈川県横浜市西区
みなとみらい3-6-3 MM パークビル3F
「みなとみらい駅」 4番出口すぐ

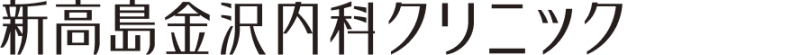
〒220-0012 神奈川県横浜市西区
みなとみらい5-1-2 ウエストタワー 2F
「新高島駅」3番出口より徒歩1分
「横浜駅」東口より徒歩8分


〒232-0024 神奈川県横浜市南区
浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス2F
「阪東橋駅」より徒歩5分

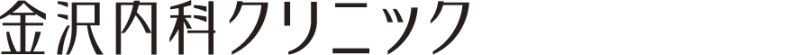
〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町341
みなとみらい金沢文庫ビル
「金沢文庫駅」東口より 徒歩1分

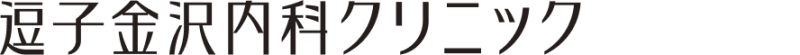
〒249-0006 神奈川県逗子市 逗子2-6-26
逗子駅前クリニックビル 1F
「逗子駅」「逗子・葉山駅」より 各徒歩2分

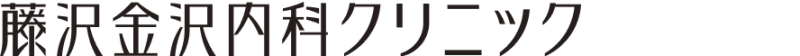
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-18
長塚第一ビル 1F
「藤沢駅」 南口より徒歩2分


〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1
アイクロス湘南1F
「辻堂駅」 北口より徒歩4分

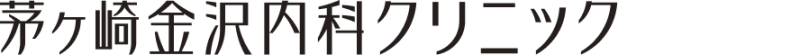
〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町22-6
ジョイ茅ヶ崎パートⅡ 2F
JR「茅ケ崎駅」南口正面 2F


〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-37-11
安与ビル 3F
「新宿駅」東口出口真横

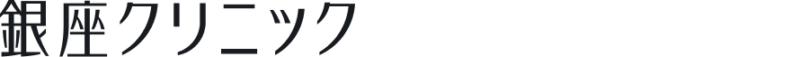
〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-6
ロンシャンビル 8F
「銀座駅」A2出口より徒歩1分

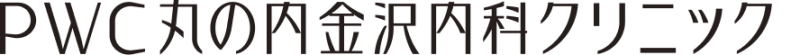
〒100-6403 東京都千代田区 丸の内2-7-3
東京ビルディングTOKIA 3階
「東京駅」丸の内南口すぐ
「有楽町駅」より徒歩5分
楽しいクリニック
うれしいクリニックを
めざしています
医療法人みなとみらいでは、医師・技師・看護師・
栄養士・医療事務など、様々な職種を募集しています。
医療法人みなとみらいでは、医師・技師・看護師・栄養士・医療事務など、様々な職種を募集しています。

























